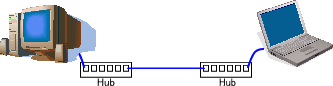
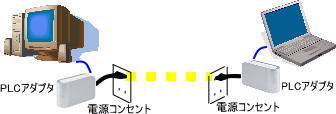
PLC(高速電力線通信)とは,既存の宅内の電気配線を通信経路としてデータ通信を行う技術です。親機と子機をセットにして,それぞれを壁の電源コンセントに差し込んで利用します。
既存の電気配線を通信経路として使用するため,LANケーブルの配線作業がなくなり非常に手軽です。
また,無線LANなどの具合が悪いような場所でも電源のラインがあれば,データ通信が可能になります。
10/100MのLANとPLCを用いたLANについて,データの転送速度を比較しました。
10/100MのLANは2台のパソコンをHubを通じて接続します(図1)。PLCを用いたLANは,2台のパソコンをPLCアダプタを通じて電源タップに接続します(図2)。
| 10/100MのLAN | PLCを用いたLAN |
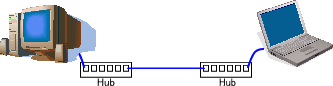
|
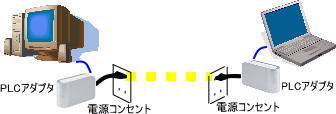
|
| 図1 | 図2 |
測定はTCPとUDPの両方で確認しました。また,値については5回以上測定したデータの平均値をグラフ化しました(図3)。
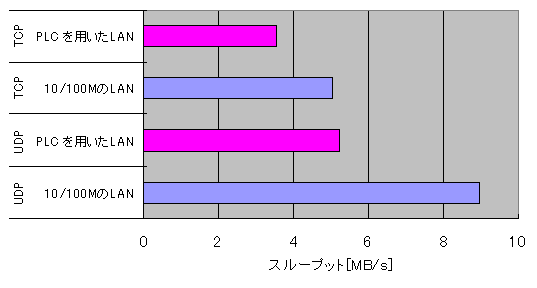
|
| 図3 |
【補足1】 この転送速度の測定にはフリーソフトのポート速度ベンチッち(RUMA作)を使用しました。
【補足2】 TCPとUDPについて
| TCPについて |
|---|
| コネクション型プロトコルと呼ばれ,通信をする前に「コネクション」を確立します。 コネクションが確立されると,通信の信頼性が保証されます。 通信の信頼性とは,「送ったデータが必ず届くこと」と「送ったデータが順番通りに届くこと」です。 これらの信頼性は,両端で何を送り何が届いたかを問い合わせ続ける事により実現しています。 メール,WWW,FTPなどでは,データが正確に伝わることが要求されます。 そのため,それらのプロトコルはTCPを使った通信を行っています。 |
| UDPについて |
| コネクションレス型プロトコルと呼ばれ,単純に「送りっぱなし」の通信です。 コネクションレス型の通信では,コネクション型のような再送は行なわれず,送ったデータが相手に届く事は保証されません。 また,受信側でパケットが送られた順番通りに届く事も保証されません。 TCPの再送や輻輳制御は非常に便利なものですが,送りなおしたり送る量を調節したりするため,データの転送に時間がかかってしまうことがあります。 UDPでは,TCPと比較して即時性があるため,音声通話や映像配信などに利用されます。 |
10/100MのLANに比べ,PLCを用いたLANのほうが数値は低くなっています。ただし,この数値はパソコン同士の転送速度を測定しているため,一概にLANの転送速度を正確に反映しているとは言えない面があるので注意が必要です。
数値の上では2種類のLANには,差があるように感じますが,実際に10/100MのLANからPLCを用いたネットワークに切り替えて運用してみたところ,Web検索やメールの送受信などにおいては速度不足と感じられることはありませんでした。
ただし,授業や実習等で多人数が同時に接続するようなケースでは,利用に際して注意が必要になることも考えられます。
PLCアダプタにパソコンを接続しない状態で,親機と子機の接続状況を検証しました。
今回,試用したアダプタは,30Mbps以上,10M〜30Mbps,10Mbps以下,通信不能,の4種類の状態を判別する機能を有しています。
検証方法は,検証の可能な限り広い部屋において,PLC接続アダプタ本体の機能を用いて行いました(図4)。
| 電源コンセントの場所とアダプタの位置 |
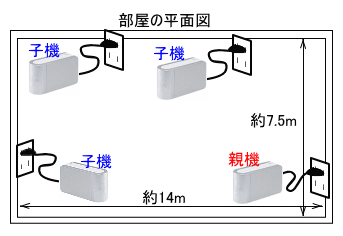 結果 |
| どの測定箇所も,30Mbps以上の表示 |
| 図4 |
同一の部屋の中においては,何の問題も無く通信が可能でした。
建物全体において,どのような範囲で接続が可能かを検証しました(図5)。
| 棟全体の接続確認 |
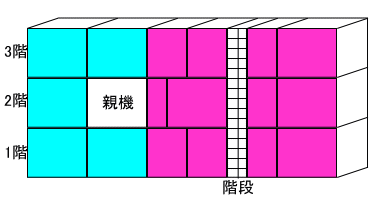 結果 |
|
■の部屋は30Mbps以上の表示 ■の部屋は通信不能の表示 |
| 図5 |
各部屋の配電状況を調査したところ,以下のような状況が分かりました(図6)。
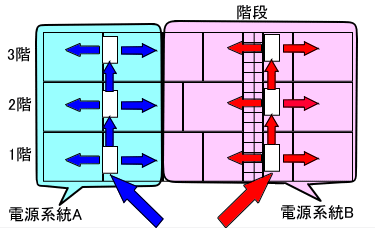 |
|
||||
| 図6 | |||||
以上のことから,通信のできる範囲は電源の系統が同一であること,通信のできない範囲は,電源が全く別の系統であることがわかります。
測定に際して,棟全体がひとつの配電系統でまかなわれている棟を確認した上で検証をしました(図7)。
| 棟全体の接続確認 |
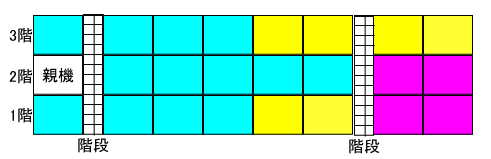 結果 |
|
■の部屋は30Mbps以上の表示 ■の部屋は10M〜30Mbpsの表示 ■の部屋は通信不能の表示 (10Mbps以下の表示を示す部屋はありませんでした) |
| 図7 |
通信不能の教室において,廊下の電源では30Mbps以上の通信表示が出た箇所もあるなど,場所によって状況の異なる不安定なところもありました。
PLCを利用する上での制限事項は実際にどの程度影響を及ぼすのか試してみました。
ノイズフィルタ機能つきの電源タップなどは,使用を避けるよう指示が明記されています。何も機能を持たない延長用の電源タップと,雷ガード付きのもの,ノイズフィルタ付きのものの3種類を用いて通信速度の測定をしました。
ア 接続の様子
親機は電源コンセントに直接接続し,子機を電源タップに接続しました(図8)。
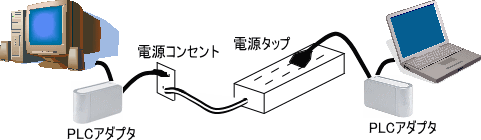 |
| 図8 |
イ 測定の結果
電源タップの種類は雷ガードつきのものとノイズフィルタ付きのものを検証しました(写真1)。
値については5回以上測定したデータの平均値をグラフ化しました(図9)。
| 電源タップの種類 | 雷ガード付き | ノイズフィルタ付き | |
| 写真1 | |||
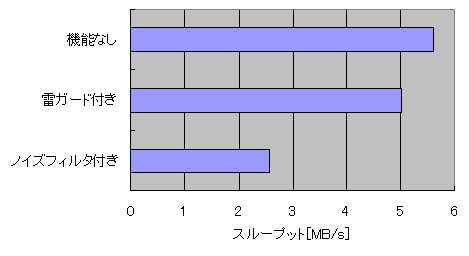 |
| 図9 |
結果からノイズフィルタの効果(影響)は相当大きいことが窺えます。
PLCを接続する同じ電源タップには,携帯電話の充電器や掃除機など,接続が望ましくないものがいくつか挙げられています。それらがどの程度通信速度に影響があるのか測定してみました。
ア 接続の様子
子機の接続されている電源タップに,携帯電話の充電器や掃除機を接続しました(図10)。
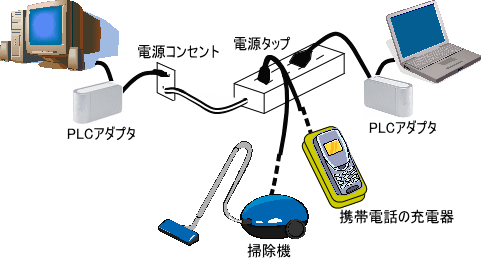 |
| 図10 |
イ 測定の結果
値については5回以上測定したデータの平均値をグラフ化しました(図11)。
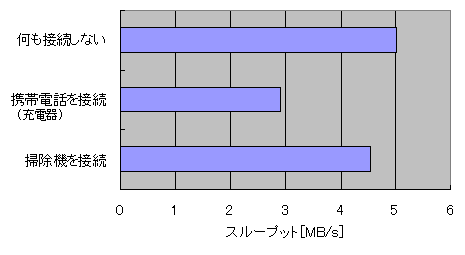 |
| 図11 |
データからは,取り扱い説明書の記述から受ける印象よりも影響が少なく感じられます。
しかし,携帯電話の充電器を接続した場合には測定中に通信が途切れることもしばしばあり,大変不安定でした。
接続が簡単なPLCですが,電源コンセントはどの部屋にもあるため,アダプタの自由(勝手)な追加によってセキュリティが脅かされる心配は無いのか,疑問が残ります。そこで,アダプタの追加についていくつか検証をしてみました(図12)。
追加用の子機を単純に電源コンセントに接続しても,当然ネットワークには参加できませんでした。
親機に認識させた後は,ネットワークに接続できました。親機に認識させる手順は非常に簡単なものでした。
ちなみに,メーカの統一は関係が無く,異なるメーカでもほぼ同様の操作で,子機の登録は可能でした。(複数メーカで検証)
セキュリティの観点からは,親機は管理者(もしくは相当する役割の人)以外は操作できないような物理的な制約を設け,アダプタの追加は管理者のみが可能にする等のルール作りが必要だと思われます。
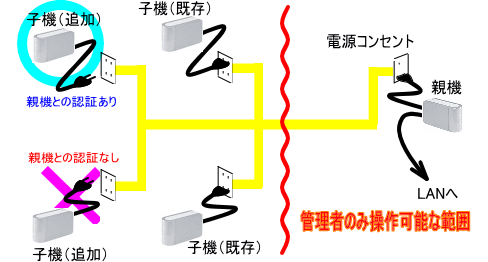 |
| 図12 |
親機の追加は即ち,同一電源ライン上に複数のネットワークを構築することを意味します。
ひと組のアダプタとパソコンのネットワークを構築した後,既に通信ができることを確認してあるもうひと組のネットワークを同じ電源ライン上に移設します(図13)。
結果はお互いのネットワークは全く干渉せずに利用が可能でした。
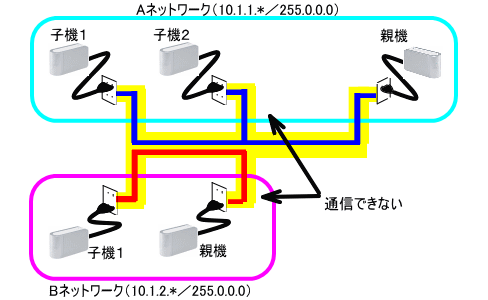 |
| 図13 |
PLCを利用したネットワークの活用には,PLC特有の利点を生かしたものが考えられます。
LANの敷設が行われていない場所において,一時的にLANがあると便利なことがあります。ただし,どのような場合でも配電系統を調べる,親機の管理を確実に行う,などの条件をクリアする必要があります。
ア 授業で用いる
職員ネットワークにデータを保存しておき,PLCを用いて教室で利用が可能になります(図14)。
職員間で共用するパソコンを教室に持ち込む場合などには,データを保存したり削除したりする手間がなくなります。
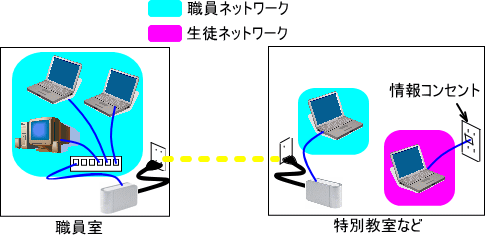 |
| 図14 |
イ 研修会場として用いる
LANの設備が整っていない場所でも,ノートパソコンのほかにLANケーブルや電源タップが準備できれば,パソコン操作をはじめとするネットワークなどの研修会場が設営できます(図15)。
職員用ネットワークだけでなく,任意のネットワークを一時的に拡張できるので,受講者にあった適切な運用が容易にできます。
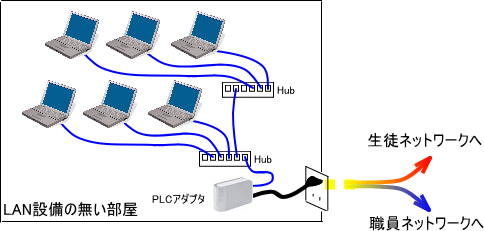 |
| 図15 |
様々な事情で工事の難しい,あるいは配線が充実していない部屋において利用が考えられます。
ア 配線が容易
電気配線と電源コンセントを利用してLAN環境をつくることができます。LANケーブルで新たな配線を作る必要がないので,今までLANケーブルが設置されていなかった場所にもLAN環境が構築可能になります。また,既存のネットワークとは別のネットワークを構築することも可能になります。
製品の取扱説明書によると距離による制約は約150mとなっていますので,比較的容易に接続できると予想されました。しかし,実際には配電系統に充分な注意が必要なことと,様々な影響を受けているようで,単純に距離だけでは接続を判断できないことが窺えます。【3 接続可能な範囲】
イ 設定が容易
設置,設定は従来,敷居が高く感じることの多かったネットワーク機器の設定と異なり電源コンセントに差し込むと自動的に概ねの設定が行われるため,大変簡単です。
ウ 高速な通信が可能
測定値でも40Mbs程度の転送速度が得られるなど,高速データ通信が可能です。
通常のLAN配線に比べると,やや物足りない印象もありますが,使用頻度や利用者数の制限・管理などによって充分実用も可能と考えられます。【2 設置と動作】
エ セキュリティ面
AES 128bit暗号技術が用いられており,事実上のセキュリティ面は高いといえると思われます。
【5 セキュリティ】で示したとおり,同じ電源ライン上に異なるLANが存在できるので,簡易的なVLANのような用途も考えられると思われます。即ち,従来だったら生徒用と職員用と2本のラインが必要だったところを,電源ライン1本と2組のPLCアダプタによって,セキュリティを保ちつつLANの一時的拡張が可能になります。
一見PLCは画期的な機器のように感じますが,まだまだ数々の問題点があります。導入する際にはこの点を理解した上で使うことが必要です。
ア 電気ノイズに弱い
PLCの一番の弱点は電気ノイズに弱いことがあげられます。携帯電話の充電器などによる影響があり,影響を受けると速度が落ちたり,通信が不安定になったります。
イ 配線・環境によって差が出やすい
データの通信経路となる電気配線の環境によって影響を受けます。PLCは親機と子機との間に使用される電線の距離が長くなればなるほど通信速度に影響を与えてしまいます。そのためそんなに見た目では親機と子機との電源コンセントの距離が短くても,壁の中にある電線が長ければその分だけ通信速度に影響を与えてしまうことになります。
また,使用されているブレーカーの種類によっては,フロア間や部屋の間の通信ができないといったケースも考えられます。そのため,電源コンセントがあればどこでも利用できるという保障はありません。
ウ PLCが与える問題点
PLCは動作中に高周波信号を使って通信しているのですが,この高周波信号が医療機器に影響を及ぼす可能性があり,最悪の場合は医療器具の誤作動により事故になってしまいます。
またPLCは,アマチュア無線,短波放送,航空無線,海上無線,電波を利用した天文観測などの無線通信している設備の近辺で使用した場合,これらの業務の妨害となってしまう可能性があります。そのため,PLCの規制緩和前はいろいろと議論が交わされ,結果屋内の利用のみでの使用であればということになりました。
しかし,上記設備に継続的また重大的に妨害の原因を作ってしまった場合は,電波法に基づき総務大臣から妨害を取り除くように命じられます。