| 1 交流計画 | |
| 時期 | 内容 |
| 5月 | ○古代米の栽培活動を開始する。 ○NHK教育番組「おこめ」を視聴する。 |
| 6月 | ○NHK学校放送オンラインで情報収集をする。 ○掲示板に小豆坂小のプロフィールをアップする。 ○交流相手校(広島市立安東小学校)と連絡を取り、交流の方針について打ち合わせをする。 |
| 7月 | ○自己紹介カードを交換し、交流を開始する。 ○掲示板に書き込みをする。 ○古代米とインディカ米をプレゼントし合う。 ○ビデオレターを制作し、送る。 |
| 9月 | ○掲示板で情報交換する。 ○古代米栽培ドキュメンタリー番組の制作を始める。 |
| 10月 | ○稲刈りをする。 ○掲示板で情報交換をする。 ○ビデオレターの交換をする。 |
| 11月 | ○掲示板で情報交換をする。 |
| 12月 | ○古代米の収穫祭をする。 ○掲示板で情報交換をする。 ○ビデオレターの交換をする。 |
| 1月 | ○古代米栽培ドキュメンタリー番組をプレゼントする。 ○掲示板で情報交換をする。 |
| 2 NHK学校放送オンラインの概要 | |
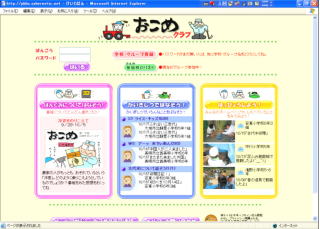 放送教育の最近の傾向では、放送教育と情報教育の相互乗り入れが強調されてきている。それは、NHKが制作を進めてきたデジタル教材が整備されつつあるためである。現在の放送教育は、放送番組を単独で視聴するだけでなく、Web上のデジタル教材を併用することでさらに学習が深まるようになっている。 放送教育の最近の傾向では、放送教育と情報教育の相互乗り入れが強調されてきている。それは、NHKが制作を進めてきたデジタル教材が整備されつつあるためである。現在の放送教育は、放送番組を単独で視聴するだけでなく、Web上のデジタル教材を併用することでさらに学習が深まるようになっている。例えば、総合的な学習の番組「おこめ」には、ビデオクリップや用語集が用意された Webページがあり、「おこめクラブ」という掲示板で全国の小学校と意見交換することができる。 同じ関心をもつ児童同士が地域を越えて交流できる場が準備されていることは、大変ありがたいことである。セキュリティーの面でも、この掲示板は登録制になっており、NHKや協力する大学などによって管理されている。また、児童の書き込んだ内容が、教師のメールに送られてきて確認できるようになっているため、 安心して利用することができる。 |
|
| 3 総合的な学習の活動 −古代米を育てよう | |
 歴史の授業で、弥生時代の米作りについて学んでいたとき、「弥生時代では、どんな品種の米を育てていたんですか」という質問が出た。しばらくして、A子が自主学習ノートに赤米と黒米の2つぶの古代米を張り付け、インターネットで調べた解説を書いてきた。これをみんなに紹介したところ、自分たちも古代米を育ててみたいということになり、種もみや苗を探すことになった。おりしも新聞で古代米を育てているグループがあることを知り、早速連絡を取り、訪問すると、親切にも7種類の古代米の苗をくださった。 歴史の授業で、弥生時代の米作りについて学んでいたとき、「弥生時代では、どんな品種の米を育てていたんですか」という質問が出た。しばらくして、A子が自主学習ノートに赤米と黒米の2つぶの古代米を張り付け、インターネットで調べた解説を書いてきた。これをみんなに紹介したところ、自分たちも古代米を育ててみたいということになり、種もみや苗を探すことになった。おりしも新聞で古代米を育てているグループがあることを知り、早速連絡を取り、訪問すると、親切にも7種類の古代米の苗をくださった。田植えでは、穂の色ごとに、赤、黒、緑、オレンジ、えんじ、白、茶の7品種から、自分の好みの苗をバケツに植えた。土には、篤農家の方からいただいたミネラルや鉱物を混ぜるなどの工夫をした。 古代米は生命力が強いが、水を切らしてはいけないため、夏休みの間も水遣り当番を決めて、大切に育てた。 また、有志の子で南設楽郡鳳来町にある千枚田(棚田)でも、4枚の小さな田んぼを借りて田植えを行った。 こちらは、千枚田保存会の方々の協力を得て、1ヶ月に一度世話をしに行っている。 |
|
| 4 交流の実際 | |
| (1)「お米を交換しよう」 古代米を育てているうちに、「本当に古代米は病気に強いのだろうか」や「追肥はしなくてよいのか」 といった疑問がわいてきた。そこでNHKの「おこめ」のページを使って調べ学習を行った。 また、古代米を通じて他の小学校と交流を行いたいと考え、掲示板を閲覧したところ、広島市立安東小学校が同じようなテーマに取り組んでいることが分かり、交流を申し込んだ。 交流を開始するにあたりそれぞれが育てている稲を交換した。小豆坂小からは7種類の古代米を送り、安東小からはインディカ米をもらった。また、学級全体同士での交流ではなく、個人の交流にしたいと考え、プロフィールをメールで交換し合い、親近感を深めることができた。さらに、お互いの顔が分かるようにビデオレターを作成して交換した。 このビデオレターの制作では、子供たちはとても生き生きと活動することができた。文字だけでなく映像をやりとりすることは子供たちにとって、より相手を身近に感じる手段なのだと感じた。これまでは、ビデオテープを郵送するという方法であったが、今後はビデオファイルをネットワーク上で送る方法を検討したい。 (2)NHK掲示板への書き込み  掲示板では、古代米の情報交換をした。古代米の栽培方法や種類などの質問をやりとりしたり、栽培の進捗状況などを伝えたりした。古代米は野生種に近いため、肥料は必要としないが、収率は現代の米に比べて良くない。さらに、今年は台風の被害が大きく、特に広島県は甚大な被害があった ようである。そのようなこともあって、稲の実りは両校ともあまりよくなかったのであるが、無事稲刈りを迎えることができた。10月15日付の掲示板に収穫の喜びを伝えるメッセージが届き、子供たちは大変喜んだ。 掲示板では、古代米の情報交換をした。古代米の栽培方法や種類などの質問をやりとりしたり、栽培の進捗状況などを伝えたりした。古代米は野生種に近いため、肥料は必要としないが、収率は現代の米に比べて良くない。さらに、今年は台風の被害が大きく、特に広島県は甚大な被害があった ようである。そのようなこともあって、稲の実りは両校ともあまりよくなかったのであるが、無事稲刈りを迎えることができた。10月15日付の掲示板に収穫の喜びを伝えるメッセージが届き、子供たちは大変喜んだ。
(3)ビデオレターの交換  互いに顔の見える交流をしたいということで、掲示板での交流と並行して映像のやり取りを検討した。小豆坂小学校ではネットワーク環境が100Mbpsの光ケーブルであるため、MPEG4などでの動画配信も難しくはないが、先方の学校がISDNであるため、インターネット上での動画のやり取りは難しいと判断した。 互いに顔の見える交流をしたいということで、掲示板での交流と並行して映像のやり取りを検討した。小豆坂小学校ではネットワーク環境が100Mbpsの光ケーブルであるため、MPEG4などでの動画配信も難しくはないが、先方の学校がISDNであるため、インターネット上での動画のやり取りは難しいと判断した。そこで1学期に始めたビデオレターの交換を引き続き行うことにした。国語科で「ニュース番組を作ろう」 という単元があり、それぞれの学校の話題やクイズ、占いコーナーなど、それぞれが工夫して制作した番組をビデオにして交換し合った。また、これまでの古代米の栽培活動をふりかえるドキュメンタリー番組を作って 送った。この活動は、インターネットを用いたものではなかったが、画像が鮮明に見られるなどの利点もあり、 一対一の交流においては、ビデオレターという方法も有効なのではないかと思う。 |
|
| 5 成果と課題 | |
| 今回の交流実践授業では、次のような成果が得られた。 <成果> ○NHK学校放送オンラインの掲示板を用いて、比較的容易にネット交流ができた。 ○ビデオレターを併用することで、互いに親近感をもって交流することができた。 ○「古代米」という共通のテーマや取組があることで、中身のある交流につながった。 <課題> ○交換し合う情報の質を高める指導が必要である。 ○ネット上での動画配信を検討したい。 |