| 生徒実習課題例 |
通学・通勤方法を考える
|
科目の中の位置づけ社会と情報(4)ウ 情報社会における問題の解決情報の科学(2)ア 問題解決の基本的な考え方 情報の科学(2)イ 問題の解決と処理手順の自動化 情報の科学(2)ウ モデル化とシミュレーション 情報の科学(3)ア 情報通信ネットワークと問題解決 情報の科学(3)イ 情報の蓄積・管理とデータベース 情報の科学(3)ウ 問題解決の評価と改善 内容実習に必要な機器、材料電卓、表計算ソフト授業プリント例 授業用プリント、確認テスト、評価規準の例を作成しました。 実習方法実習1 通学方法を考えよう。(1) 通学経路の説明 甲君は、新しく進学することになった学校までの通学時間について、いくつかの通学路や交通手段を検討した。 甲君の自宅から学校までのルートは、以下のようになっている。 晴天時、雨天時、積雪時における乗物等の平均速度は、図のようになっているものとして、次の(1)から(6)の通学方法を用いたときの通学時間を算出し、最短時間のルートを探しなさい。 ただし、バス停と駅での乗り降りにかかる時間は5分として加算するものとする。 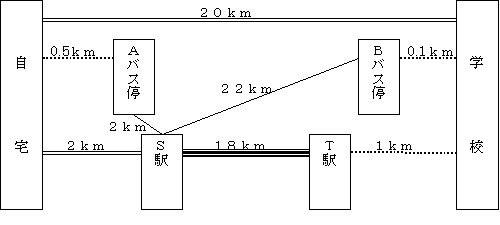
(2) 課題 次のa.からf.の通学方法を用いたときの通学時間を算出し、最短時間のルートを探しなさい。 ただし、バス停と駅での乗り降りにかかる時間は5分として加算するものとする。 通学方法 (その1):通常の場合
通学方法 (その2):突発的な事故が発生した場合
(3) 考え方 次のような表を作成する。
電卓等を利用するか、表計算ソフトを利用して、それぞれの値を計算することにより、最短ルートを調べる。 実習2 通勤方法を考えよう。 (1) 通勤経路の説明 甲さんは、遠距離通勤者で、毎日、1時間以上をかけて通勤している。その通勤経路は次のようである。
私鉄のK駅からは、図2のような時刻表で電車がある。また、この電車で座ることのできる確率も図2に記入してある。私鉄のS駅 またはN駅で降りて、地下鉄に乗り換える。
地下鉄の路線はレッドライン、ブルーライン、グリーンラインがある。 レッドラインはN駅、F駅、I駅を通る。ブルーラインはN駅、T駅、M駅、I駅、L駅を通る。グリーンラインはG駅、M駅、F駅、L駅、を通り、A駅が終点である。ここから、私鉄に乗り換えるが、ほぼ1本ごとに、直通でZ駅まで行く電車がある。 地下鉄の路線図は、図3、それそれのラインの時刻表および座れる確率は図4から図6のようである。 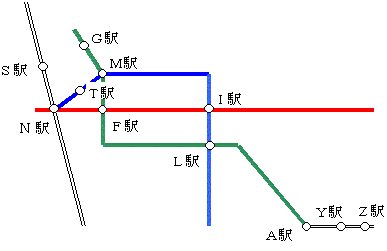 図3 地下鉄の路線図
(2) 課題 次のa.からc.の場合について、最適な方法を考えなさい。
(3) 考え方
応用実習
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間配分 150分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間配分 | 生徒の動き | 教師の動き |
| 15分 |
学習内容
|
実習の目的の説明 実習1の課題の説明
|
| 35分 |
実習1
|
計算については、電卓、表計算ソフト等を適宜利用する。 コンピュータの利用にこだわらない。 巡回し、補足説明。 電卓を利用した場合と表計算ソフトを利用した場合とで、作業効率について考えさせる。 結果を記入した表の回収。 |
| 10分 |
学習内容
|
実習2の課題の説明
|
| 40分 |
実習2(その1)
|
巡回し、補足説明。 |
| 40分 |
実習2(その2)
|
発表について、相互評価および自己評価する。 ( |
| 10分 |
実習内容
|
次時の予告。 自己評価シートの回収。 相互評価シートの回収。 |