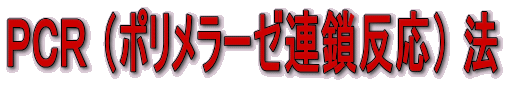
| back |
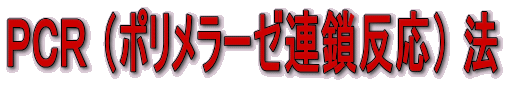 |
| 1 はじめに |
|
DNAの塩基配列の決定や遺伝子組換えなどの遺伝子操作などを行うときには、目的とするDNA断片が多量に必要である。PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)法を用いることで、目的とするDNA断片を短時間で、大量に増幅させることができる。 マリス(Kary Babks Mullis、アメリカ)は、1983年にPCR法を開発し、1993年に、この業績に対してノーベル化学賞が贈られた。PCR法は、その後の遺伝子工学の進歩に大きく貢献した。 |
| 2 PCR法に必要な酵素とDNA断片 |
| (1) DNA合成酵素(DNAポリメラーゼ) | ||
|
鋳型(いがた)となるDNAのヌクレオチド鎖を基にして、ヌクレオチドを重合する酵素。PCR法では高温(72℃)で反応する耐熱性のDNA合成酵素が用いられる。この酵素は、海底火山などの熱水噴出孔に生息する好熱菌Thermus aquaticus から分離精製されたのでTaqポリラーゼとも呼ばれている。 |
||
| (2) DNA断片 「プライマー」 | ||
| DNAの合成を開始するのに必要な短いDNA断片(20〜30塩基程度) | ||
| 3 PCR法の原理 |
| (1) ステップ1 | 変性 | 94℃で2本鎖のDNAは水素結合が切れ、1本鎖DNAに解離する。 | |
| (2) ステップ2 | プライマーの結合 | 55℃に冷却するとプライマーが、1本鎖DNAの相補的な塩基配列の部分に結合する。 | |
| (3) ステップ3 | プライマーの伸長 | 72℃にするとDNAポリメラーゼが働いてプライマーを伸長させる。これで1サイクルが終了し、再びステップ1に戻る。 |
| 3回のサイクルでDNA量は8倍になる | 20回のサイクル(数時間)で100万倍になる(グラフ) |
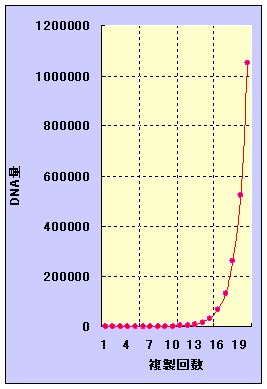
|
| 4 PCR法で使用する試薬・器具・機器 |

|

|

|
| back |