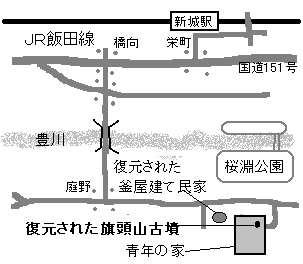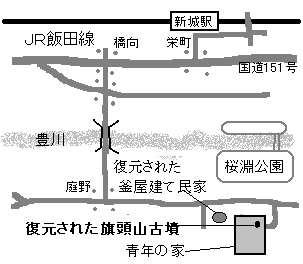釜屋建て民家(かまやだてみんか) <時代>江戸時代 <地域>東三河
 |
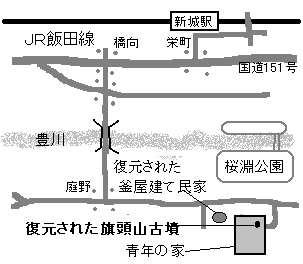 |
| (桜淵公園内に復元された釜屋建て民家) |
|
<所在地> 新城市黒田高縄手7(JR飯田線新城駅から豊鉄バス富岡線黒田下車徒歩15分)
新城市庭野桜淵公園内(JR飯田線新城駅下車徒歩25分)
<概要>
釜屋建て形式の民家の建築様式は,豊川流域と天竜川下流域のみに見られる,非常に珍しい建築様式である。新城市黒田の望月家(もちづきけ)住宅はその原型をよくとどめているとして,1974年(昭和49)国の重要文化財に指定された。建物は主屋(おもや)と釜屋(かまや)がT字形に直交するように左右に建てられている。釜屋に入ると右側に馬屋があり,左側に風呂場がある。奥は「奥にわ」と呼ばれ土間になっており,夜なべ仕事や冬期・雨天時の仕事場であった。主屋は田の字形の間取りで,「おでい」・「おえ」・「へや」・「だいどこ」の四つの部屋がある。「おでい」は座敷,「おえ」は居間で,「へや」は寝室,「だいどこ」は現在の食堂に当たる。どの部屋も押し入れはなく縁側も付いていない。
<学習のポイント>
江戸時代の農民の生活についてその住居の形式から具体的にイメージしたい。馬屋が家の中にあるところもおもしろい。
<見学のポイント>
望月家住宅は黒田に現存するが,現在は新城市の桜淵公園内に復元された釜屋建て民家があり,見学することができる。
<参考資料>
「新城市誌」 「図説東三河の歴史」 「東三河の歴史」 「愛知県の歴史散歩」
<問い合わせ先>
新城図書館(ふるさと情報館) 0536-23-2333
愛知エースネットへ トップへ