愛知県総合教育センター研究紀要 第98集
実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究(最終報告)
| 独立行政法人科学技術振興機構(JST)が開発した「理科ねっとわーく」などのデジタル教材を活用した学習指導を実施し,その効果的,効率的な活用の在り方を19年度に引き続いて研究した。実証授業として小・中・高等学校23校でデジタル教材を活用した実践を行った。デジタル教材の活用は,授業に対する興味・関心を高め,理解を深めることができるが,授業分析の結果,デジタル教材を提示する前に視点を与える,提示しながら行う説明を工夫する,提示後に定着を図るために確認の発問をするなどの授業技術と授業構成の工夫を行えば,より効果的であることが分かった。 |
検索用キーワード |
|
|
| ||
| 小学校部会 中学校部会 高等学校部会 連携先 |
一宮市立西成小学校教諭 |
加藤 英恵 江口 拓 間瀬 彰宏 岩本 聡子 鈴木 宏記 松浦 明伸 杉村 定則 寺澤 益実 小田 泰史 足立 敏 古川 敦朗 柳生 真澄 米津 利仁 小林 夕也 牧原 秀一 岩月 迅美 山畑 真樹 杉嶋 重男 金廣 伸也 鶴見 泰文 野口 裕生 松宮 誠 川手 文男 坂田 貴仙 宇野 弘重 岡村 直樹 櫛田 敏宏(主務者) 吉田 淳 |
| 1 | はじめに |
|
児童生徒は,身の回りの体験や経験を土台に,想像力や推理力を駆使し,自然の事物・現象をモデル化したり,イメージ化を図ったりしながら科学的な知識や概念を獲得していく。しかし,近年の生活体験の不足により,想像力や推理力が低下し,このモデル化やイメージ化がうまくいっていないという問題がある。そこで,デジタル教材を授業に用いることにより,児童生徒の想像力や推理力が補われ,モデル化やイメージ化が円滑に進められるのではないかと考えた。 |
|
JST「理科ねっとわーく」の特徴 |
| 2 | 研究の目的 |
|
理科における児童生徒の興味・関心や知的探究心等を育成するために,デジタル教材と,観察・実験等の体験的活動とを融合した効果的かつ効率的な学習指導の在り方を明らかにする。 |
| 3 | 研究の方法 |
| (1) 研究組織 19年度は,教育研究調査事業「教科指導の充実に関する研究(理科C)」において,校種ごとに部会を設け,小・中・高等学校(研究協力委員小学校部会6名,中学校部会6名,高等学校部会5名)の相互の連携を図りながら研究を推進した。また,愛知教育大学と綿密に連携して会の運営及び研究推進に当たった。 20年度は,高等学校の研究協力委員を増やし,教育研究調査事業「教科指導の充実に関する研究(理科A)」において,校種ごとに部会を設け,小・中・高等学校(研究協力委員小学校部会5名,中学校部会4名,高等学校部会15名)の相互の連携を図りながら研究を推進している。また,19年度と同様に,愛知教育大学と綿密に連携して会の運営及び研究推進に当たっている。 (2) 研究方法 19,20年度とも,研究会を年間5回程度実施し,ねらいの設定及び達成に向けた意見・情報交換等を行った。研究協力委員の所属校でデジタル教材を活用した実証授業を前期(5,6,7月)と後期(10,11,12月)に各1回ずつ行った。実証授業には,センター所員,大学教授等が立ち会い,デジタル教材活用の在り方の分析・検証等を授業者と共に行っている。また,実証授業ではビデオ撮影や事前・事後アンケート等を行い,研究会における検討資料とした。 また,20年度においては,デジタル教材を授業改善の手段として,活用すべきであるという視点から,「どういう場面でデジタル教材を活用し,それによってどのような学習効果が上がったかという点を明らかにすること」を中心に研究を行う方針を立てた。そのためには,教師の発問や子供の受け答えにまで踏み込んだ,細かな授業分析から効果的なデジタル教材の活用を明らかにすることが重要と考えて実証授業を行ってきた。 |
| 4 | 研究の内容 |
|
(1) デジタル教材利用の基本姿勢 |
| (2) 実証授業の計画 19年度は,実証授業に先立って,平成19年5月8日と5月13日に,東海学園高等学校 小林夕也教諭による,デジタル教材を用いたモデル授業が実施された。実証授業は,小学校部会12回,中学校部会12回,高等学校部会が8回,合計32回が実施された。なお,小学校部会1回,中学校部会2回,高等学校部会1回の合計4回の実証授業を公開授業とし,その地区の多くの教員の参加を得て,研究協議を実施した(19年度の実証授業に関しては,別冊の研究報告書をご覧いただきたい)。 20年度の実証授業(資料1参照)は,小学校部会10回,中学校部会8回,高等学校部会が28回,合計46回を実施した。なお,小学校部会1回,中学校部会1回,高等学校部会2回の合計4回の実証授業を公開授業とし,19年度と同様に,その地区の多くの教員の参加を得て,研究協議を実施した。 なお,実証授業では,デジタル教材の内容,活用法により下記のように分類した(資料1参照)。 |
|
Ⅰ 内容による分類 |
|
(3) 事前・事後アンケートの実施及び結果 |
| グラフ1 問 「理科は好きですか」 | ||
|
前期 |
後期 | |
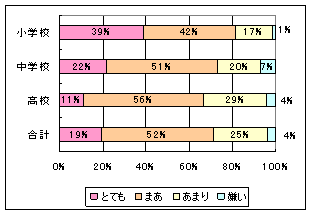 |
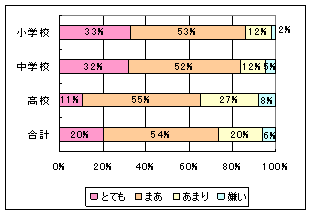 |
|
|
高等学校は,「理科が好きですか」ではなく,「化学Ⅱが好きですか」のように,受けている授業科目として聞いた。前後期とも,「好き」という回答は,小学校が高く,中学,高等学校に進むに連れて低下している。昨今の各種調査と比較すれば,今回対象となった母集団の理科が好きな度合いは,格段に高い。 |
|
グラフ2 問 「次の単元では,デジタル教材(コンピュータの映像)を授業の一部に使います。デジタル教材を用いた授業は,楽しみですか」 |
| 前期 | 後期 | |
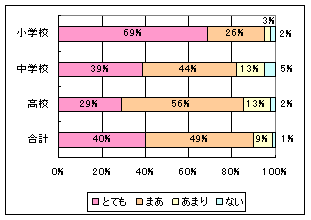 |
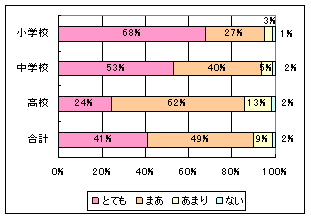 |
|
全体で9割程度の児童生徒がデジタル教材に期待していることが分かる。各校種において,前期と後期であまり大きな変化はなかった。前期に中学校の期待度が若干低かったが,後期は,19年と同程度まで上昇した。デジタル教材を用いた授業を受け,好感をもったからではないか。 |
|
グラフ3 問 「デジタル教材を使うことによって,興味や関心は高まりましたか」 | ||
| 前期 | 後期 | |
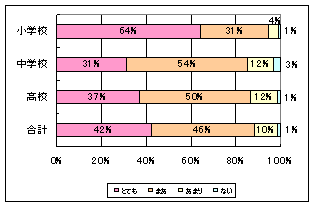 |
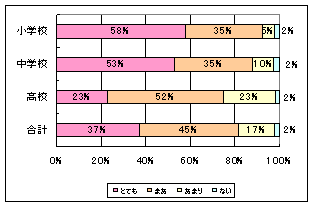 |
|
|
グラフ4 問 「デジタル教材を使うことによって,授業の内容が分かるようになりましたか」 | ||
|
前期 |
後期 | |
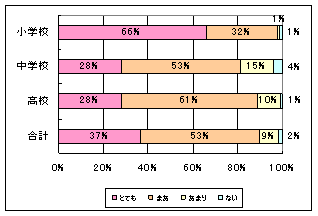 |
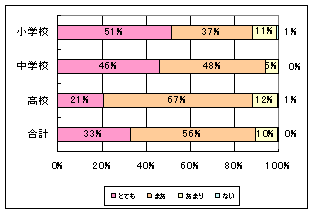 |
|
|
グラフ5 問 「今後もデジタル教材を用いた授業を行ってほしいですか」 | ||
|
前期 |
後期 | |
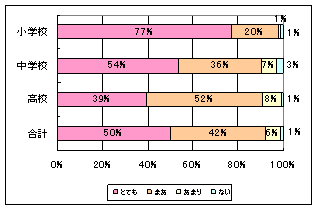 |
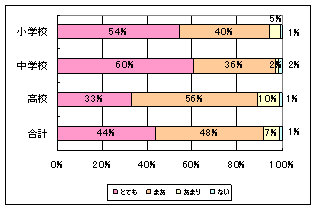 |
|
|
各校種の興味・関心の高まりについての肯定的な回答は,全体で若干下がっているが8割を超えている。授業の理解度については,中学校が若干上昇しているが,全体的には大きな変化はみられなかった。今後のデジタル教材活用への期待については,小・中学校が若干下がっているが,全体的には大きな変化はみられなかった。多くの問いで小学校の肯定的な回答が高く,続いて中学校,高等学校の順であった。 |
| 5 | 研究のまとめと今後の課題 |
| (1) 19年度のまとめ 19年度の研究協議会では,実践及び協議の中でデジタル教材を授業で効果的に活用するためには,活用意図の明確化,活用方法の習得,利用方法の工夫の3点に留意することが大切であるという考えで一致した。 ・デジタル教材は,使う場面によってその効果が異なるので,児童生徒の状況や指導意図,学習内容に合った活用を図る(活用意図の明確化)。 ・必ずしもコンピュータの利用にこだわることなく,教科書や指導計画に合わせたデジタル教材を整理し,これらを任意に取り出して活用することで教科指導をより深化・充実させる手法を確立する(活用方法の習得)。 ・教員一人一人によって,活用の仕方や使い方は異なってくるが,児童生徒にとって効果的,効率的な活用モデルを確立する必要がある(活用方法の工夫)。 JSTの「理科ねっとわーく」への大きな要望としては,コンテンツにはよいものも多いが,授業意図に合うように活用しようとすると事前の準備に手間が掛かる。もう少し手軽に扱え,加工も容易な素材集的な編集にした方がよいということを提言したい。 本研究の実践として,小・中・高等学校17校でデジタル教材を活用した授業実践を行った。アンケート結果からは,多くの児童生徒がデジタル教材に対して,大きな期待をもっていることが分かった。デジタル教材を様々な方法で活用し,活用回数も増えた結果,教師側としては,厚みのある授業になったと考えられた。また,生徒側としても,デジタルコンテンツを利用した授業を受け入れやすくなったと考えられた。 (2) 20年度のまとめと今後の課題 20年度は,教師の発問や子供の受け答えにまで踏み込んだ,細かな授業分析から効果的なデジタル教材の活用を明らかにすることを目標にした。小中学校の授業を中心に,愛知教育大学と連携し,実証授業を撮影したビデオ映像から,教師の発言,子供の発言を細かく分析した。その結果を資料3,4に示す。授業分析の成果として,デジタル教材を提示する前に視点を与える,提示しながら行う説明を工夫する,提示後に定着を図るために確認の発問をするなどの授業技術と授業構成の工夫を行えば,より効果的であることが分かった。 今後,授業分析の結果を集積し,効果的なデジタル教材の活用方法についてまとめていくことが重要である。コンピュータに関する機器の整備が一定程度進んだ現在,デジタル教材を効果的かつ効率的に活用することは,理科教育の充実に大変有用である。 参考文献 1) 独立行政法人メディア教育開発センター 文部科学省委託事業 「教育の情報化に資する研究(ICTを活用した指導の効果の調査)報告書」平成19年3月 |
資料1 実証授業一覧
資料2 実践校アンケート一覧
資料3,4 授業分析結果
|
実践編 |
| 【実践1】小学校5年 | 理科「たんじょうのふしぎ」 | |
| 【実践2】小学校2年 | 生活科「おもちゃまつりをひらこう」 | |
| 【実践3】中学校3年 | 理科「細胞と生物のふえ方」 | |
| 【実践4】中学校1年 | 理科「光や音,力で見る世界」 | |
| 【実践5】高等学校3年 | 物理Ⅱ「直流回路」 | |
| 【実践6】高等学校3年 | 化学Ⅱ「課題研究」 | |